インタビュー
「本」の形をした絵を描くことで、移り変わる自己と世界との距離感を測る。〜4期生インタビュー Vol.14 田村正樹さん〜
クマ財団が支援する学生クリエイターたち。
彼らはどんなコンセプトやメッセージを持って創作活動に打ち込んでいるのか。
今という時代に新たな表現でアプローチする彼らの想いをお届けします。
>>> 4期生のインタビューについての記事はこちらから。
4期生41名のインタビュー、始めます!
田村 正樹

1995年栃木県生まれ。2018年、多摩美術大学 絵画学科油画専攻卒業。
現在、東京藝術大学大学院修士課程在籍。
近年は「本」の形態をした絵画を中心に制作している。
ページをめくることで生まれる時間的・空間的広がりを利用しつつ、内的イメージを膨らませて、自己と世界との間の「距離」を探っている。
「藝大の猫展2020」コンペティション「猫アートプラザ賞」受賞。
https://kuma-foundation.org/student/masaki-tamura/
ページをめくる時間性によって、絵に物語が生まれる
――「本」の形態をした一風変わった絵画を制作されていますが、こうした表現に至るまでにはどんな変遷があったんでしょうか?
田村 中高一貫校の美術部に入っていて、中学生のとき初めて油絵を描きました。顧問の先生がものをしっかり観察して描くことの基礎を徹底的に教えてくれたので、その頃は写実的な作風で描いていました。それまでは図書館にある美術全集の知識がすべてで、電車に乗って東京の美術館へ近代絵画を観に行くことが僕にとって非日常的な楽しみという感じでしたが、多摩美術大学に入って初めて現代アートの世界を知ったんです。
油画を専攻していたんですが、パフォーマンスや映像制作といった絵画とは別のことをしている人がかなりいて、とても刺激を受けました。アートという大きなくくりの中で見たとき、これまで自分がやってきたことは一部の狭い領域だったことに気づかされて、「もっといろんなことができるんだ」と考え方が変わっていきましたね。それから油絵だけでなく、漫画、インスタレーション、ホワイトシートの壁画など、いろんな方法で作品を制作するようになったんです。
――絵画を「本」にするという表現は、どんな発想から生まれたものなんですか?
田村 多摩美術大学を卒業してからは会社に就職して働いていました。就職するか進学するかで悩んだ時期もあったんですが、美術の外のことも含めていろんな経験を積みたい気持ちもあって、カルチャーセンターで講座を企画する仕事に就いたんです。普段は会社員として日々を過ごし、日常生活で感じたことがいつか絵にフィードバックされればいいなと思っていて、タイミングが来たときに作品化したいと考えていました。

芸大アーツイン丸の内2020(2020.10.24〜31)にて、作品を展示した。
――必ずしも職業化しなくても絵は描き続けられますよね。働きながら描いていたんですか?
田村 その間はあまり描いていませんでしたが、頭の片隅には常に絵のことがありました。会社で働きながら、もう一度、絵を描こうとなったとき、やはり絵を描く場所と時間が欲しいと思いました。それで愛知県立芸術大学に学びたい先生がいたので、研究生として半年ほど愛知に行くことにしたんです。そこで創りはじめたのが、本の形態の作品でした。
なぜそうした形態になったかというと、僕は昔から本を読むのが好きで、小説に関心があったり、大学時代に友達と漫画を描いていたこともあって、いつか時間性を持った作品を創りたいと考えていたからです。研究生には広いスペースのアトリエを使える環境がなかったこともあり、自室の狭い空間でも制作できるから、という現実的な理由もありました。
――本ごとにテーマや世界観があるようですが、ストーリーはあるんでしょうか?
田村 一貫したストーリーというものはありません。だけど、ページをめくることで次の絵につながったり、見開きで見たり、前のページに戻ったりというふうに本特有の前後関係があるので、おのずと時間性が生まれてきますよね。描くにおいても前のページの絵が次のページの絵に自然と影響をおよぼしてきます。そうした本の持つ時間性の中で、一枚一枚の絵に物語が生まれると思っていて、絵をきっかけにどのようなストーリーを読むかは、鑑賞者に委ねられています。
――ストーリーがないとしたら、絵のインスピレーションはどんなふうに湧くんですか?
田村 それが制作していく上で一番大切にしている部分です。今は4冊目を創っているところなんですが、それぞれにカラーが決まっているんですね。1作目が『The Book of Kite』という題名で“凧”の本なんですが、これは自分と世界との距離感を表しています。僕は現実世界を「地面」、自己の内面を表す空想世界を「空」というふうに見立てているのですが、“凧”というのは、「地面」と「空」の間をふわふわ漂っているイメージです。僕が絵を描くときは空に意識がいくんですが、空の彼方に行ってしまうわけではなく、一本の糸で地面とつながっていて、地面には糸を持っている自分がいる。現実と空想の間で漂いながら、自己と世界との距離感を測るようにして描いているんです。

「The Book of Kite」(2019年)
現実世界から刺激を受けて反応した結果が、僕の作品
――1作目が現実から空想の世界に浮かぶイメージだとしたら、2作目、3作目はどんなコンセプトなんでしょうか?
田村 2作目は『The Book of Drops』で“雫”の本になります。1作目がやや空想寄りになりすぎたので、2作目はあえて現実世界にイメージを引き寄せようと思って描きました。空から降ってきた雨粒がだんだん下に落ちていって地面(現実世界)に向かうという方向性になります。
3作目は『The Book of Cloud』で“雲”の本です。地面につながれていた糸は断ち切られ、空に浮かんでいる状態ですよね。自分はもう糸を持っていなくて、地上から移り変わっていく雲を見上げているイメージです。「異者の書」というサブタイトルを付けているんですが、人間世界から離れ、異星人や魚がたくさん出てきます。それぞれの本で距離の測り方を意識的に変えているので、3冊を見比べてもらうと面白いと思いますね。

「The Book of Drops-からっぽバケツのブルース-」《表紙(エンプティ・フォレスト、宙吊りガール)》(2019-20年)
――今描いている4作目は、どんなイメージなんですか?
田村 描きながらテーマが決まってくるので、まだはっきりと決まっているわけではないですが、3作目よりもだいぶ現実寄りになって、日々の「生活」みたいなものがテーマになってきそうです。こんなふうに方向性だけがあって、今日は何が描けるだろう?という出たとこ勝負みたいな気分で絵に向かうんです。その時々の自分の心情や自分の変化というものに誠実でありたいと思って描いていますね。
――「本」というものは、作者の世界の捉え方や個人の内面を読むようなところがありますが、表現は違えど、田村さんの作品はそれに近い印象がありますね。
田村 多摩美術大学の卒業制作で高さ7メートルの壁画作品を創ったんですが、あのときは公衆の前で演説するようなイメージで描いていて、それとは対照的に本は鑑賞者一人ひとりに語りかけるようなイメージで描いています。本というものは、時間や場所に捉われず、個人的にひっそり読むことができるものですが、今の自分には、一対一の関係性の中で鑑賞者とつながることができる「本」というスタイルがしっくりきているんだと思います。
「本」の作品を制作しはじめたとき、自分と絵の距離がぐっと縮まった気がしました。自然と「自己の内面」や「自分が見ている世界」というものに興味が湧いてきて、今までは外から借りていた主題を自分の内に見出すことができるようになりました。
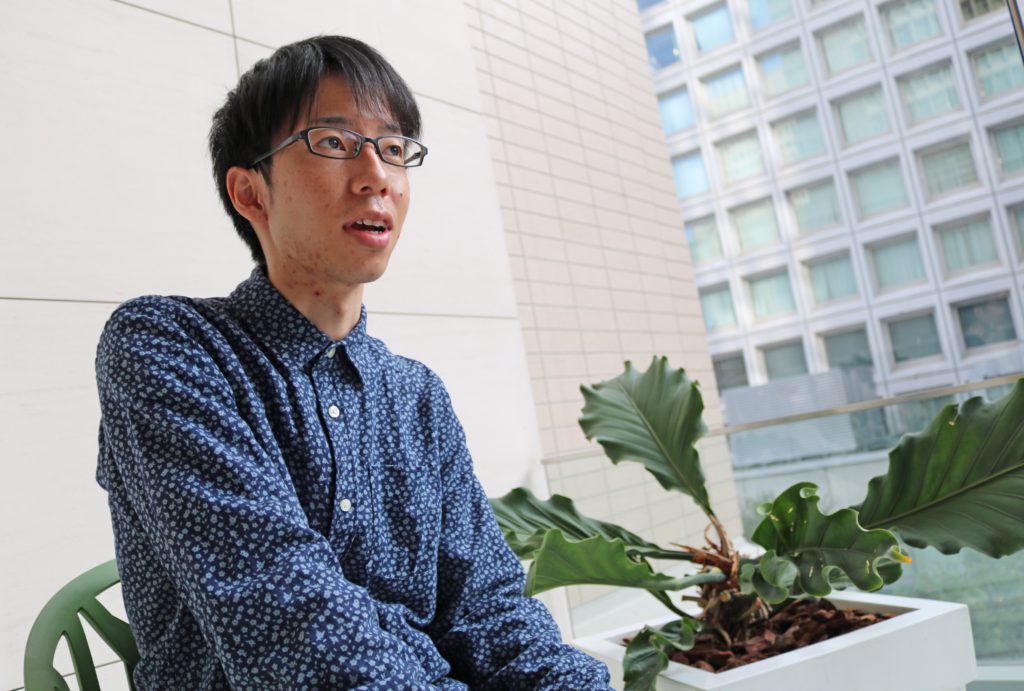
――田村さんから見えている今の社会は、どんな捉え方なんでしょうか?
田村 僕にとって「社会」とは、日々の中ですれ違う街の人々や、偶然、電車に乗り合わせた人々の暮らしの中にあるものだと思っています。彼らの日々を想像してみることが、僕にとって「社会」を考えることなんです。個人の数だけ見ている世界が存在し、その世界は見る人によっていかようにも変化していくものだと思います。無数に存在する世界の断片があって、僕は僕の視点からこの世界と向き合い、他者の世界を想像しながら本の1ページ1ページに落とし込んでいく。それが一冊の本に結実したとき、ほんのわずかでも、この世界を理解する手がかりになるんじゃないかと考えています。
――今後はどんな作家になっていきたいと考えていますか?
田村 「作家性=自分のアイデンティティ」のようなものだとすれば、それが変わっていくほうが自然な気がしています。「確かな自分というものはない」という考えが僕のベースにあって、自分とは周りの環境によって形作られていくもの。そう考えると、人との出会いや縁も、きっと偶然であって必然なんですよね。自分に深い内面世界があって、それを表現しているというより、外からの刺激を受けて反応した結果が、僕の作品だと思っています。今は「本」の作品が一番しっくりきていますが、人との出会いによって変わっていく可能性も十分あると思います。
――本日はありがとうございました!

展示が行われた、丸ビルにてインタビュー
Text/Photo by 大寺明