インタビュー
活動支援生インタビュー vol.50 Yeji Sei Lee「韓国の「母」と自己の関係性を見つめて」
クマ財団では、プロジェクトベースの助成金「活動支援事業」を通じて多種多様な若手クリエイターへの継続支援・応援に努めています。このインタビューシリーズでは、その活動支援生がどんな想いやメッセージを持って創作活動に打ち込んでいるのか。不透明な時代の中でも、実直に向き合う若きクリエイターの姿を伝えます。
活動支援生インタビューシリーズについての記事はこちらから。
活動支援生インタビュー、はじめます!
Yeji Sei Lee
11月17日(金)〜12月9日(土)、東京のTHE LOOP GALLERYで、李晟睿智(Yeji Sei Lee)の個展「“Call me by my name”」が開催されている。李は1995年東京生まれ。現在、東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻に在籍している。これまで絵画表現を主軸に、アイデンティティの所在をさまざまな角度から見つめようとしてきた。本展では、ドイツへの交換留学をきっかけに向き合うことになった、李自身の母と祖母との関係性に焦点が当てられている。「大文字の歴史ではない個人史を伝える方法について考えたい」と語る李に、本展の着想にいたった経緯や、各作品の制作背景などについて伺った。
聞き手:小林 紗由里

個展「“Call me by my name”」展示風景 THE LOOP GALLERY 2023
「母」の存在について考えたきかっけ
──昨年交換留学で行かれたドイツ・ミュンヘンでは、韓国人留学生や他国の留学生との交流が増え、それが本展のテーマである「母」の存在や関係性について考えるきっかけになったそうですね。
李:現地のある留学生と韓国出身のお互いの母親について話したとき、教育や美容に対する熱心さなど、私たちの母親のこだわる点があまりにも似ていることに驚きました。また、私が近年影響を受けた作品のひとつに、ミシェル・ザウナーの『Crying in H Mart(Hマートで泣きながら)』(2021年)という、韓国人の母親との思い出を綴ったエッセイがあります。その中で彼女は、母親が顔に化粧水をパッティングする音を丁寧に描写しているのですが、それが自分の記憶とリンクしていてとても興味深かったんです。私の所感では、韓国の母親が娘に対しても「肌や姿勢を美しく」と言うのは、皆が理想とする美を追い求めるためではなく、最も自分に自信が持てる状態を維持してほしいからなのだと思います。また、勉強に関しても、当時(母の世代)の韓国は裕福な人がいる一方で、まだまだ貧しい人も多く、教育を受けることに対する悲願の念みたいなものもありました。こうした留学生たちとの対話を通して、母親たちが口にする厳しい言葉の裏には、それと同じくらい愛情があるのだと改めて気付かされました。
──同じルーツを持つ留学生との会話や、韓国出身の母について書かれたエッセイを読むことで、お母様の新たな一面を発見し、言語化できるようになったのですね。
李:はい、母について、自分の中できちんとカテゴライズされた感覚というか、以前よりも母を認識できるようになった感覚がありました。ほかに影響を受けた作品では、ドイツの知人に勧められた韓国系アメリカ人作家ミン・ジン・リーの小説『パチンコ』(2017年)もあります。この作品には作家の自伝的な要素もあり、大文字の歴史には残らない個人史のようなものを紡いでいく手法にとても影響を受けました。私がアートを通してやりたいことは、まさにこの小説のようなことだと思いました。
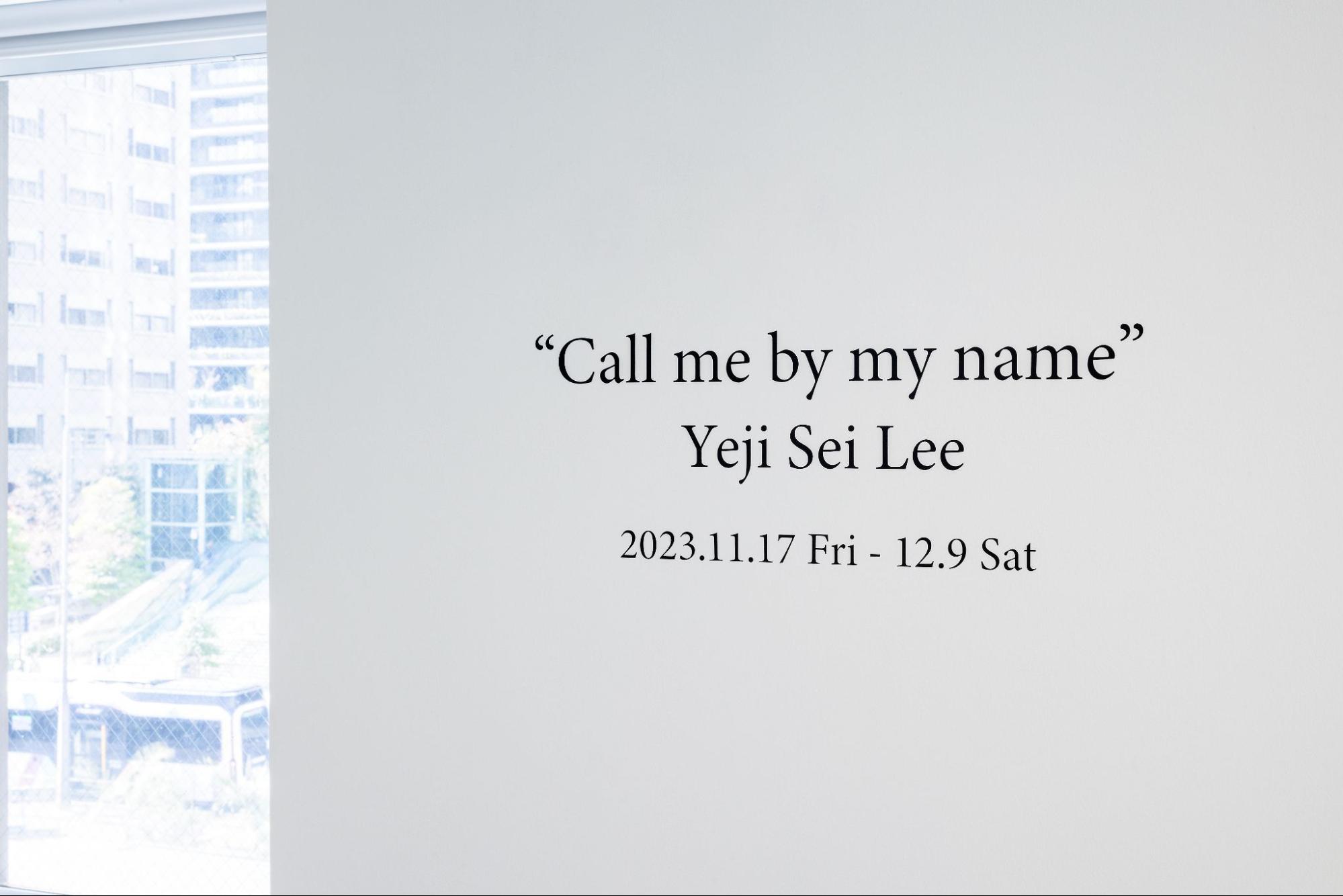
個展「“Call me by my name”」展示風景 THE LOOP GALLERY 2023
──(韓国の)母と娘の関係に焦点を絞って本展を構成された背景がよくわかりました。このテーマを通して、本展で特に鑑賞者に伝えたかったことはなんでしょうか。
李:一番は、世の中の「母」に注目が集まるものをつくりたかったというのがあります。社会が大きく変わり、家事労働の大変さなどはより認識されるようになりましたが、「母親」という存在はいまだ、社会的に賞賛されない部分を多く担っていると思います。母である人、母であった人、母になるかもしれない人たちのことも考えながら、「母」という存在を見つめなおしていくことが、今回の試みの根底にありました。
今回の出品作品について
──本展の写真作品《母娘の日常会話》(2023年)は、丁寧につくられたお弁当のビジュアルが目を引きますね。この作品はどのような背景から制作されたのでしょうか。
李:今年の4月に大学院の修士2年目を迎えたのですが、おそらく学生生活も最後かもしれないということで、母にお弁当をつくってほしいということを伝えていました。先ほど話した、韓国にルーツを持つ作家や韓国人留学生との出会いを通して、やっぱり韓国文化は食が中心に始まることをすごく痛切に感じたんです。先ほどのエッセイ『Crying in H Mart』には、各章ごとにご飯のエピソードが出てくるのですが、それを読むと、作者にとっても私にとっても、ご飯はコミュニケーションのツールのひとつだったということがわかりました。

《모녀의 일상 대화》(母娘の日常会話) 2023 紙にインクジェットプリント、アルミニウム、樹脂、木材 30 x 40 cm(1点)
──ではこれらのお弁当も、母と娘のコミュニケーションのひとつのかたちとして現われているのですね。
李:そうなんです。コミュニケーションや会話を主題にした作品をこの展覧会に入れることはとても重要だと考え、制作しました。私が学部生の頃、母と喧嘩をして2か月くらい口を聞いてもらえなかったことがあったのですが、そのときも毎日ずっとお弁当はつくってくれたんです。毎朝卓上にお弁当だけが置いてあって。
──無言のコミュニケーションという感じですね。
李:そうですね。これがコミュニケーションなんだと認識してお弁当を食べると、母が何も言わなくても私の様子を五感で感じ取ってくれているようで、その答えが「ごはん」として出てくる。また、お弁当の文化というのはもちろん韓国にもあります。今年の5月に母と韓国に行き、母が通った通学路を見て、昔の話を聞く機会がありました。母の世代は貧しい家庭もあったので、今日はお弁当を持ってこれたけれど次の日は持ってこれない同級生もいたりして。そんなときはみんなでお金を出し合ってお餅を買ったり、おかずを少しずつシェアしてあげたこともあったそうです。このように私と母とで、世代ごとに食のコミュニケーションが異なるということも興味深く思いました。
これらの写真は、毎日自然光の入るスタジオの一角で撮りました。私の個性が極力出ないように、母の作品を母のものとして見せるように心がけました。食事が生活の中心にあることを大切にしている母の生き方を享受している私は、それをリプリゼントすることならできると思ったんです。

《Call me by my name》 2023 木製パネルにキャンバス、油彩、木炭、アラビアガム、顔彩、石膏 560 x 200 cm
──《“Call me by my name”》(2023年)はスケールが大きく圧倒されました。これはどのような主題の作品なのでしょうか。
李:この作品は、私の祖母に対する印象を統括して描いたものです。祖母は釜山にある大きな市場の一角に店を構え、魚を売っていました。また、この絵は母のために描きたいという気持ちもありました。母は韓国よりも日本で生活している時間の方が長いのですが、韓国はここ20年でとても変わり、母が戻るたびに彼女がそこにいた形跡というのも薄れてきていると思います。それゆえ、祖母のことを描くことによって、母の記憶の所在を一度固定してあげたいという気持ちもありました。
──この作品は、市場の写真などを参照しながら制作されているのでしょうか。
李:今回、1960年代から90年代の釜山がどのような様子だったのか知りたくて、釜山広域市立市民図書館に行って昔の資料を何枚か印刷してきました。まず、それらの資料と以前に撮った市場の写真をパソコンに取り込んでコラージュをつくり、だいたい5~6割が完成したところで、キャンバスに移行して全体をつくり上げていきました。また、今回の展示では、絵に当てる照明をその日の天候によって調整しています。韓国の市場をまわると、白熱球がとても明るいお店もあれば薄暗い場所もあり、光のバリエーションが沢山あることに気づきます。人の声、匂い、光が目まぐるしく変わる躍動感みたいなものが作品を通して追体験できるように、舞台セットのような照明の効果で、絵の前に立つ人がより作品に没入できるよう工夫をしています。

《엄마의 등》(オンマ(母)の背中) 2023 キャンバスに油彩、アクリル絵の具 116.7 x 72.7 cm
──《オンマ(母)の背中》(2023年)は、お母様をモデルに描かれたのでしょうか。
李:はい、これは母の背中を描いています。今回母をどのように描こうか考えたとき、彼女がよくキムチを漬けていたのを思い出しました。一度母に裸の背中を描きたいといったら、恥ずかしいので嫌だと断られたんですね。では銭湯に一緒に行こうと。そこで母の背中を見たのですが、手仕事や家事をやっているとどうしても背中は丸まりますよね。でも、そこには自分と家族を支えるためにできた厚みや重みがあると思ったんです。今までの西洋絵画でも女性の後ろ姿は様々なかたちで描かれてきましたが、私の場合は純粋に、こうした母の背中を描きたいと思って制作しました。
──今回のようにご自身の家族に焦点を当てた作品は、以前からつくられていたのでしょうか。
李:これまでは、自分の主体性を介在させない作品の方が多かったです。自分のルーツや見てきたものをベースに何かを表現することはありましたが、外的な要素から引っ張ってきたものを再構築するような作品がほとんどでした。一方、家族というのは私にとって非常にパーソナルなもので、こうしたテーマでの作品発表ははじめてです。ただ、考えてみれば、学部1年生のときに初めて描いた市場の絵は、今回の作品とつながりがあるかもしれません。この絵は、私が藝大に入って最初に描いた大作です。

《DONGDAEMUN MARKET》 2016 キャンバスに油彩 162.0 x 97.0 cm
──今回の大作《“Call me by my name”》(2023年)をまさに彷彿とさせる絵ですね。
李:美大生としての私の絵はこのイメージからはじまり、同じようなイメージの作品で終わるのだという気がしますね。

個展「“Call me by my name”」展示風景 THE LOOP GALLERY 2023
空間へのこだわり
──今回の展示では、床に置かれたスピーカーから流れている音も印象的でした。
李:これは自分の息を編集しています。母と祖母と自身の関係性を展覧会で見せるにあたり、今の自分のポジションをどうやって展覧会に投影できるか考えていました。あるとき、制作中に坂本龍一のピアノ曲を聞いていたんですが、ピアノの音色とともに演奏者の息遣いも録音されている楽曲があり、それがすごく素敵だなと思ったんです。展示の1~2週間前に思い付き、音楽をやっている友人のスタジオ録音に飛び入り参加させてもらい収録しました。
──音や照明など、展示空間に様々な工夫を凝らしているのが伝わりました。李さんは、個展は一つのインスタレーションであるとおっしゃっていますね。こうした作品の見せ方において、影響を受けたアーティストはいるのでしょうか。
李:影響を受けた作家のひとりはマーク・ロスコです。18歳くらいのときに学校の授業でDIC川村記念美術館に行き、はじめてロスコの部屋を見て、舞台の中にいるような感覚を覚えました。それ以降、絵画は見るものではなく、経験するものであると考えるようになりました。当時そう思ったというより、美大で美術について学ぶうちに、あのときのことはこういうことだったんだなと気づいていった感じです。ニューヨーク近代美術館でもロスコの作品をみましたが、照明や空間の大きさ、椅子の有無などがここまで絵に作用していたのかということを実感しました。
また、2019年にシャーマニズムをリサーチするため2か月ほど韓国に滞在したのですが、そこでテンプル・ステイをしました。お寺では朝、108拝というお経を聞く体験をしました。韓国の108拝ではお経を唱えながら立ったり座ったりするので、日本のお経よりも声に抑揚がつくんです。その時の声が内臓に響く感覚は、なぜかロスコの部屋での体験に似ているように感じました。私が表現したいのはこうした感覚で、いつもそれを目標に展示空間をつくっています。
個人史を編むことについて
──絵画表現のなかで、李さんが特にこだわられていることはなんでしょうか。
李:私が絵を描くときに大切にしているのは、絵の中に重低音があるか、どれだけ重さがあるか、という点です。重さといっても物理的なものではなく、画面の強度的な意味です。それは手の技法というより、心の技法と言えるかもしれません。画面を完成させるにあたって、絵には人それぞれの質量があると思います。私の場合、その質量には匂いや喧噪、湿度みたいなものが含まれます。今回はそうした要素が顕著な市場の場面を描いた作品もありますが、市場を描かなかったとしても、その対象の匂い、湿度、温度が伝わらないと自分の絵は完成しない。そうした要素を画面のなかでつくりだそうとすると、必然的に自分が求める重厚感が生まれてくる気がします。

(右)《나와 우리 할머니》(私と私のおばあちゃん) 2023 キャンバスに油彩 162 x 130.3 cm
──画面の中で抽象的な部分と具象的な部分を分けて描いている感覚はあるのでしょうか。
李:私はいつも具象的な作品を描いているように思います。印象主義的な感じで自分はものを描いている感覚がある、つまり、ナチュラリズムをやりたいわけではなく、ある印象を表現したいということです。ただ、その印象が他者に伝わるラインというのも心がけています。
──作品を通してある「印象」を伝えたいという視点は重要であるように思います。李さんの作品のテーマを考えると、アーティストによっては韓国の歴史的な資料など、リサーチに基づいた展示物を使うこともあり得ると思います。その一方で、「印象」を強調した点はなぜでしょうか。
李:まず、余白のある展覧会をつくりたいという思いがありました。そして、史実を伝えることが私の役割ではないと思っています。学部から修士課程に進んだ当初、史実と表現の間をどこまで行き来するかで悩みました。ただ、私の表現手法はあくまでペインティングがメインなので、史実に正確にアプローチすることは研究者の役割だと考えています。また、いわゆる「大文字の歴史」を教育のなかで教えられる歴史とするならば、私は「小文字の歴史」を個人の物語として重要視しています。つまり、私がやりたいのは大文字の史実ではなくて、個々の人々の物語をデリバリーしたいということです。こうした思いが制作のなかで一貫しています。

個展「“Call me by my name”」展示風景 THE LOOP GALLERY 2023
──お話しを聞く中で、「母」という存在を含め、公的な歴史には残らない個人の生に着目する李さんの視点が垣間見えた気がしました。近年、女性の社会的役割を考え、ジェンダーやフェミニズムの視点に立った作品への関心が高まっています。今後もこのようなテーマで作品を展開していく予定はありますか。
李:私の制作の一番根底にあるのは、アイデンティティの所在をさまざまな角度から見つめることです。前回の個展も自分のアイデンティティを見つめるものでしたが、そのときはスケールがより広範囲だったと思います。そして今回、母のことを考えたとき、母は私のアイデンティティと切り離せない存在です。これまでフェミニズムを語る作品を積極的につくってきたわけではありませんが、フェミニズムについて強く主張したいというよりは、母について語ると、必然的にフェミニズムやジェンダーについて考える方向になるという感覚です。今後も必要に応じて母のことを語る必要があればそうすると思いますが、今のところはこの展覧会のテーマだけを掘り下げるつもりはありません。私は、人々がどのように自分自身のアイデンティティを形成し、それを解釈し、向き合っているのかに興味があります。例えば、ドイツやヨーロッパに行くと多くの移民を見かけます。しかし、日本のような島国に移民として来ると、欧州とは異なる文脈のなかで特異な経験をすることになります。制作のうえでも、こうした移民とアイデンティティの問題を継続的に考えていきたいと思います。