ニュース
インタビュー
活動支援生インタビュー Vol.3 川端 健太 金澤水銀窟個展『SPECTRUM』
クマ財団では、プロジェクトベースの助成金「活動支援事業」を通じて多種多様な若手クリエイターへの継続支援・応援に努めています。このインタビューシリーズでは、その活動支援生がどんな想いやメッセージを持って創作活動に打ち込んでいるのか。不透明な時代の中でも、実直に向き合う若きクリエイターの姿を伝えます。
活動支援生インタビューシリーズについての記事はこちらから。
>活動支援生インタビュー、はじめます!
Kenta Kawabata | 川端 健太

現代的な視覚体験を一貫したテーマに絵画、彫刻表現を繰り広げ、鑑賞者を魅了する川端。今夏8月に、石川県金沢市に位置する金澤水銀窟にて個展『SPECTRUM』を開催した。このインタビューでは、個展企画開催までの制作プロセスや込めた想いと気づきを伺いながら、川端の表現の目指すところを紐解いてゆきます。聞き手はクマ財団1期の卒業生であり、彫刻表現を主軸に活動をする吉野 俊太郎が務める。
以下文章
インタビュアー・ライター:吉野俊太郎
事務局メンバー: 野村善文
個展「SPECTRUM」を終えて
個展展示作品と会場の様子
今年8月7日(土)から8月28日(土)にかけて石川県金沢市の金澤水銀窟にて行われた個展「Spectrum」お疲れ様でした。今回の展示はどのように望まれましたか?(野村)
川端:今回の個展会場があった石川県金沢市は「まだ現代美術を観られる環境が少ない」という話を事前に伺っていて。金沢って工芸は盛んなんですけど、絵画や彫刻を観たりっていう人はそんなに多くないらしい……そんな中で展示の機会をいただきました。
美術を観たり買ったりするのがまだあまり一般化していないであろう都市部以外の環境で個展を開催するというのは、やってみたかったことでしたし、何より有意義なことだと思い、実施することにしました。
今回の展示自体は……自分がやりたい、描きたいなと思っていることは結構一貫していて、それをどう具現化していくかが作家として試行していることなんですけど……なので自分がやりたいことを少しずつカタチにしていく機会として、今回の制作期間はちょっと短かったんですが、実験的に行ってみました。
個展を終えて、今どんなことを考えていますか?(野村)
川端:留学を予定していたり一つの作品と長く向き合いたいと思っていた事もあり久しぶりの展示でした。シンプルに格好つけずに描いていこうっていうことを改めて感じている、そんな感じです。
“格好つけずに”?(野村)
川端:作家として活動していくために作品作りに限らず様々な事を意識する中で、一線で活躍されている作家さんとか、キュレーターやギャラリストの方々などお話を伺う機会が、去年と一昨年くらいは増えたんです。
そうした中で制作していくと無意識に「自分が作っているようで、自分が本当に作りたいものを全然作っていない」という、作らされているような感覚になる事があるなって思ったんです。
今振り返ると経験としてそれはすごいよかったと思うんですけど、その先「作らされている感覚がある作品」を描き続けてもなんも良いことないなって、虚無感すら覚えてきて。とにかく自分が実感を持てることが一番大事だって改めて思って、自分が描く意義とか、その実感を持てる事をちゃんと大事にしようって意味で、“格好つけずに”、と。
―なるほど、実感持てるかどうかは重要なことですよね。
【眼って適当なんだ——ものをどうやって視るか】

KUMA EXHIBITION 2021での発表をしたtoneも展示された。
ーここから作品について詳しく伺えればと思います。個展の記録、僕も興味深く拝見しました。過去のインタビューでは卒業制作作品でもあった《vague》について「自分の目で見たものを記録せず〔=写真を見て描かずに〕、自分の中の記憶を頼りに描い」たと説明されていましたが、今回の個展で発表された作品でもそれは同じなのでしょうか。同じモチーフで複数の違った図像を作るというのが、それぞれどういった手段を経由して行われているのかが気になります。
川端:作品を作るときの素材として「何かだけ」ということは最近はあまりやっていなくて、なるべくいろんな手法で、なるべくいろんな角度から見ようという風に思っているので、多様なメディアを通して検討しようとしています。
たとえば写真を撮ったら、その写真からドローイングをするとか。それでなんか、写真からは出てこないようなカタチがドローイングをしていると出てきたりとか。人物だったら型取りをして、複製を作ってみたり…とにかく思いつく限りの手法と素材を介して描いています。
その中でも、最近はドローイングを繰り返し描くことが多いですね。いろんなところを通して、ひとつのメディアから出てくるだけじゃないカタチを探していますね。
ーコピーやスキャンを繰り返していった末にどんどん画像が粗くなっていき、結果写された対象の抽象度が増してしまうというのは現代においても多々見られる現象だと思います。写真論にも通じるようなお話ですね。
川端:そうなんです、写真とか視覚とか、そういったものが興味深くて。物事を視る時には“層”が必ずあるな、ということが自分の中でのテーマだったので、金沢での個展もレイヤーというか、細分化する……ひとつの作品の要素をいくつかに分けるみたいな意味合いで「tone」とタイトルをつけていたんです。
描かれている図像と色が分かれていたりだとか、モチーフは同じだけど、作品ごとに分けた違う描き方をするみたいな風に。当たり前だと思っていたけど実は現代特有だったりするようなものの見方とかを絵に落とし込めるように、レイヤーをイメージするような感じで作品を作っていることが多いですね。

tone11 2019 w2273×h1818mm panel.pencil.acrylic emulsion
ーそういえば《tone11》では眼を開いている人物の反射は、眼を閉じた姿で描かれていました。この作品の前後から、眼に対する意識も川端さんの中で変化があったのではないかなと推察するのですが、そうすると、卒業制作以前以後のそれぞれの作品における眼球に対しての描写の在り方にも違いが見えてくるような……。近年の作品ではだんだんと鑑賞者の側に顔を向けなくなってきているなと思うんです。《tone》で傘に隠れた人物もそうですし、卒業制作以前の作品《persive》などでは2人の人物像が向き合う状態で展示されることの多い1対の作品でしたが、金沢で展示されていた似た構図の作品では、見つめあっていたはずの人物の片側は姿を消しています。
川端:たしかに眼球についてとか、そういうのも興味を持ち始めたのがちょうど学部4年生くらいの頃で……「眼ってめちゃくちゃ適当にできているんだなー」みたいな(笑)
人間は視覚から受け取る情報の割合が比較的多いと思うのですが、色々調べたりしているとめちゃくちゃ適当にできていることがわかったんです。たとえば人間の眼球は、色彩は前方の狭い範囲でしか認識できていないようで、それ以外の視野では想像というか、記憶から作りこんでいるらしい。だから視野の外から見たことのないものを視界ギリギリに置くと、実は色は認識できておらず、モノクロームに見えている……そういう風に「眼って適当なんだ」ということを理解してから、少しずつ意識が変わっていきました。

アトリエには様々な書籍が並ぶ
ー気がつかなかった、衝撃ですね……。あとは過去作品から拝見していると、作品数枚を一群とした制作が増えてきたように感じます。3枚組や5枚組の作品など、一見して同じ図像を描いているように見えるんだけれども、それぞれ像の表れ方が微妙に異なっている。今回の個展でもそういった組作品が比較的多かったと思いますが。
川端:「ものをどうやって視るか」というのが僕にとって大事なテーマなので、それをどう作品に落とし込むかということを考えた結果、「ひとつのモチーフで複数の違う作品を描こう」と思いついたところから始まっていて。それが「KUMA EXHIBITION 2021」でも発表した《tone》辺りから自分の中では始まっていて、今も続けています。
個展では、花が朽ちていって、いわゆるドライフラワーのようなかたちになっていく様子などをひとつのモチーフにして4枚組の作品を描いたりとか(《untitled》)、ほかに人物や、空の作品(《untitled》)なども同じ図像だけど、上にある色が違うだけで……。
その色っていうのもシルクスクリーンで上から刷った四角い、ピクセルをイメージした図像の色が変わっていくだけで、同じ空の図像だけれど夕方を想起してしまうような、絵の中の時間軸がずれていってしまう……同じモチーフで違ったことを表現していく、みたいな感じです。
ーシルクスクリーンも使われているんですね。
川端:はい、自分で調合したメディウムと版を使って刷っています。色々なフィルターやノイズのようなものが物事を見る時に介在している感じを描いてみたくて、層をイメージして一つ一つの要素を分けて描くことでそういった事が表現できないかなと思って。それでどうやったら分けられるかなっていうので、モノクロームの描写の上に、シルクスクリーンでそのモチーフの固有色を乗せることで分けようかなと。

【写真という層】
ー二段階に分かれているんですね。イメージとして眼に飛び込んでくる図像と、あとそうではなく写真や絵画などのメディアを表すようなツヤだったりその照り返しだったり、もう少し素材的な表現とで分かれて表れている、まさに“層”の印象を受けます。
川端:そうですね。最近そういったところに興味があって。あと今は、写真ががめちゃくちゃ溢れている中で、物事を見ようとしたりそれを平面にしようとした時に、無意識的に「写真」っていう「層」が必ず影響していると思っていて。
たとえばヤンファンエイクのデッサンってすごく上手じゃないですか。一方で最近ニュースとかで見る「神童現る」みたいな、めちゃくちゃ絵の上手い子がいるよっていうのを見るんですけど、完全に写真っぽいんですよねなんか、絵が。で、エイクらの昔のデッサンなど、写真が無い、普及していない時代に生まれた絵には写真を感じない。直接ものを見て描きとっている感じがするんですけど、最近のいわゆる上手って言われる人の絵とか観るとなんか感じるんですよ、「写真」という要素が間にあるのを。
で、なんかそういうのって絶対要素としてあって、切り離せないし、生まれた時からあるので。それは作品を描く上で僕も現代人だからどうしようもないし、要素として考えていくことはしたいなと思ってます。描き方もこういう感じなんで写真との差異についてはずっと考たえてきたので、今は切り離すのでなく内在する要素として考えるようになりました。絶対に写真的な視覚体験を通して見ているし、人物を見る時も平面に描く時にも、それが頭に通らないわけがないと思ってます。
ー写真というものによって作り上げられてしまったものの見え方からは逃れられない部分が、現代にはあるはずですよね。
川端:シルクスクリーンで刷っているドットの大きさっていうのは、いわゆる“画質が粗い”というような意味を汲み取ることができるよなとか。なんかピントが合う/合わない的な言い方をすると、合う要素と合ってない要素っていうのを同じ画面内に含みたい、というか。
そういうところから、違うものの見え方を一つの、画面だったり制作の中に取り入れたいっていう動機から始まっていますが、次はまた違う感じで作品に落とし込みたいなっていう風にも思ってます。
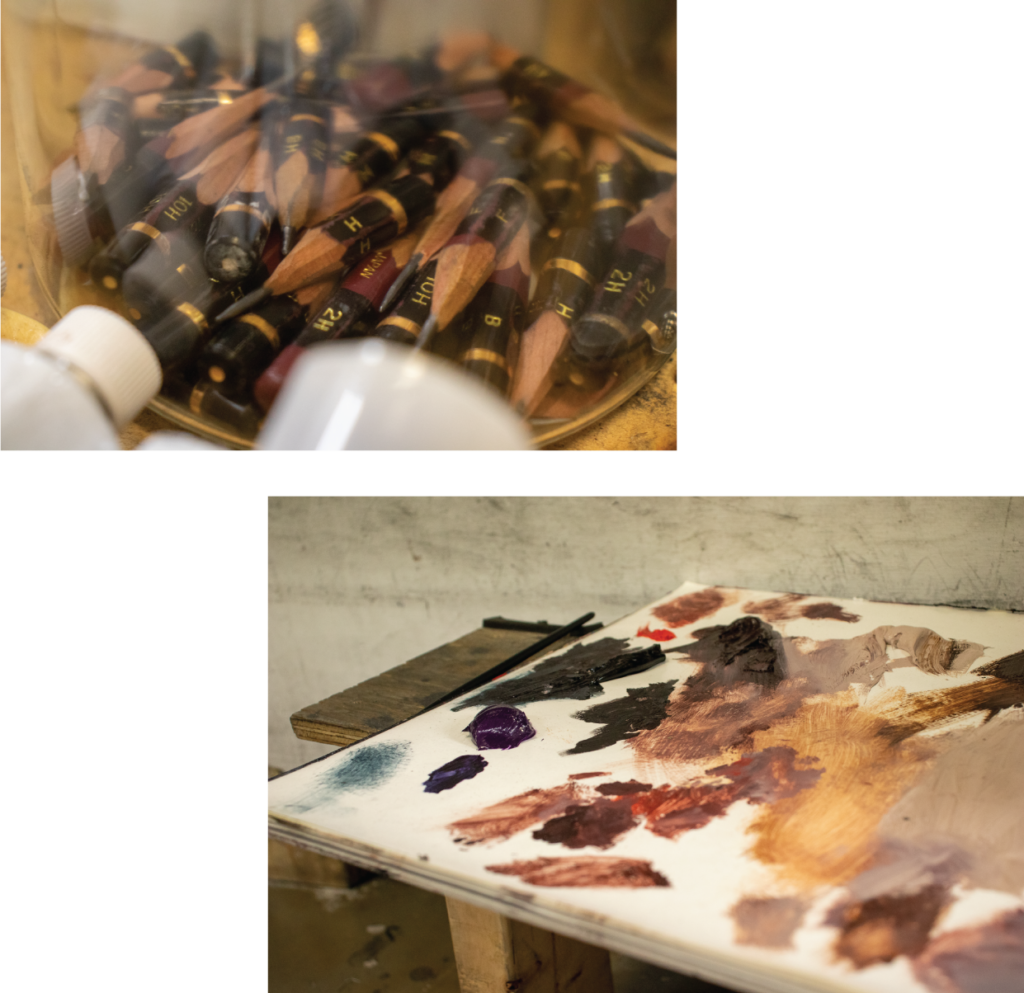
アトリエの様子
【写り込みから考える、記録の在り方】
ー個展で展示されていた《tone》は「KUMA EXHIBITION 2021」でも発表されていたものですよね。あらためて拝見していると、川端さんの作品では表面に施されたニスがかなり強烈に効果しているように感じられます。
川端:これはまあ作品に依るんですが、観ている側が作品に、服や体の色が視認できるくらいに強く写り込んだりするもので、僕の作りたいものの中では要素としてすごく大事になっています。
ーなるほど。記録写真を拝見している限りではとても綺麗で鮮明に作品の様子が記録されているのですが、これまでお話を伺っていると、実は撮影者が篩い落としてしまった、写り込みのある写真こそが川端さんの作品の理想的なあり方なのではないかとも思ってしまいました。「記録は記録だから」と割り切りの必要な部分と、逆に作品コンセプトとしては綺麗に写すことの難しさが残されていることの重要さ。それらの共生し難いアンビバレントな関係がとても興味深いです。
川端:そうですね、そこはすごく難しくて。個展では写り込みを残したまま撮影したりもしてみたので、今後はそういった記録も残していこうかなと思ったりもしています。
ーそれは面白そうですね。昨今のアーティストたちの中にはTino Sehgalなどのような作品記録に対する作家的応答をする者も見られますし、そういった態度が川端さんの作品への解釈を助けてくれることも今後あるかと思います。今回お話を伺ってみて、川端さんが作品を通して探求していることの一端を垣間見ることができたように思います。絵画というのは視覚へのアクセスの痕跡とも喩えられると思うのですが、川端さんの作品ではむしろそこから視覚の不確実性の話へと繋がってくる点が刺激的でした。しかしだからといってご自身の眼球の内に自閉する態度をとっているわけでもない。眼を疑い、眼とともに絵を描き続ける——その二面性こそが川端さんの作品の魅力の一つを担っているのだと思います。
修了作品での展開はどのようなものになるのかがますます楽しみになる内容でした、本日は本当にどうもありがとうございました!
